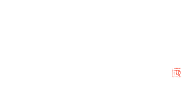昭和に生まれて令和を駆ける
2020.5.12
私は昭和46年生まれ。
昭和生まれ、昭和育ち、平成を歩み、令和を駆ける。
駆けだした令和早々に、こんな大きな出来事が
起こるとは思いもよらなかった。
しかし、よく耳にする感染拡大防止を「国民一丸」
というフレーズから「昭和」を連想した。
私が生まれ、育った「昭和」は
「ぬくもり」溢れる時代だった。
生活用品には木製品が多く、木製品といっても
合板や加工されたモノではなく、無垢材である。
住宅はもちろん、まな板、しゃもじ、木桶、
木の「ぬくもり」に包まれて育った。
無垢材だけでない。「裸電球」もそうだ。
薄暗いが、「ぽっ」と温かい明かりを灯してくれる。
LEDにも「電球色」はあるが、明らかに違う。
私だけだろうか?そう感じるのは。
またデジタルが標準である今の若者には、
「音が悪い」と評価が低い「真空管」。
そっとレコードに針を落とすも「バチッ」と
「生音」が入る。
肌に溶け込むような「優しく」「温かみ」
のある低音がスピーカーから流れた。
家族には「臭い」と不評だが、
い草が香る畳も大好きだった。
夏休み、昼寝が好きだった私は、薄着で寝そべり、
畳の目を顔に写しながら、呼吸する畳と共に
寝息を立てた。
そんな「モノ」が五感に「ぬくもり」を
伝えてくれたのが「昭和」だった。
「ぬくもりあるモノ」は「人」が生み、
育ててくれたもの。
「昭和」は「ぬくもりあるモノ」が溢れる時代.
と同時に「人のぬくもり」が溢れた時代であった。
ここで、私が「昭和の象徴」として紹介したい
出来事がある。
私が小学2年生の時のことだ。
当時私は父の転勤で、神奈川県川崎市に住んでいた。
最寄りは私鉄小田急線の「生田」という駅で、
駅から徒歩10分ほどの住宅街に父、母、祖母、
兄2人の計6人で暮らしていた。
当時、母は「親友の会社を手伝う」と言って
西日暮里の食品工場までパートに出ていた。
いつも帰りが遅い母の代わりに、祖母が私達の
面倒をみてくれた。
「さみしいな」なんて言葉を口にしたことはないが、
母が恋しくなると「お母さんを迎えにいこうか」
と言って、兄と二人、小田急電車に乗って仕事場に
押し掛けた事もあった。
そんな母を迎えに行った帰りの事、
帰りの通勤ラッシュに巻き込まれた。
ラッシュといっても
今とは比べ物にならない混雑である。
列車が出発する直前に、
駅員が扉付近にいる乗客を押し込む。
そこに入り込もうとする乗客をまた押し込む。
また入りこむ。押し込む。
ひどい時には駅員が背中で押し込む。
「もう入らない」というところまで。
今では考えられない。
コンプライアンス?
そんなものは存在すらしない。
しかし、田舎から出てきた私達にとっては
その混雑が新鮮だった。
兄と「おしくらまんじゅう」をしながら、
笑いがこぼれた。
しかし、笑いもつかの間。
私達は降りる出口扉から反対側の扉まで押し込まれ、
全く身動きが取れなくなった。
しかも、私たちが降りる「生田」駅は
降りる人が少ない。
とても降りられる状態ではなかった。
「これは降りられないな・・・」
「どうしよう・・・」
と不安を漏らす兄と私に母は、
「次の次の駅でおりましょう。これは無理だわ。」
「いや降りようよ」
「無理・・・」
そんなやりとりをしているうちに生田に着いた。
かすかに扉が開く音が聞こえた。すると、
「ワッショイ、ワッショイ」
と大きなかけ声が聞こえた。
かけ声に合わせて、私達の周りに居た乗客が、
私達三人の背中を押し、列車から出してくれた。
とにかく驚いた。
むしろ「出られた」という喜びが先に勝った。
私は息苦しかった車内から解放され、
新鮮な空気を肩で大きく吸い込み、
ようやく気持ちを落ち着かせた。
そんな私をよそに母は、動き出す電車の乗客に
向かって手を振っていた。
「よかった・・・」と安堵した私の言葉を、
母は「あたたかい」という言葉で遮り、
助けて下った「恩人たち」に感謝した。
幼い私ではあったが、今でもその日の出来事は
はっきりと覚えている。
見ず知らずの困っている人に、
見ず知らずの人同士で助け合う。
躊躇なく、その場で一つになれる。
それが昭和は「自然」だった。
「人」が「人」にぬくもりを注ぐ。
「ぬくもり」に対し、心から感謝する。
感謝とその喜びを、また別の「人」に注ぐ。
そんな「ぬくもり」溢れる時代が「昭和」だ。
昭和生まれ、昭和育ち、平成を歩んだ私は
令和にこの「ぬくもり」を伝えていきたい。
「おせっかい」と言われながらも。